近年、働き方改革や物流需要の変化に伴い、トラックドライバーの働き方や走行距離にも大きな変化が見られます。
昔と比べてドライバーの負担は軽減されているのか、逆に走行距離が増えているのか、気になる人は多いのではないでしょうか。
この記事では、昔と現在の走行距離の比較、背景にある社会の変化、現場の課題、今後の展望まで詳しく解説します。
運送業に興味のある方や、キャリアを考えるドライバーの方はぜひ参考にしてください。
昔のトラックドライバーの走行距離
かつてのトラックドライバーは、現在と比べて過酷な環境で長距離を走行していました。
| 時代背景 | 内容 |
|---|---|
| 高度経済成長期 | 大量輸送需要の急増により、1日数百キロ、月間1万キロ以上走行が一般的だった |
| 労働規制の緩さ | 労働時間や休憩規制がゆるく、深夜・長時間運転が常態化していた |
| 物流インフラの未整備 | 高速道路や物流拠点が少なく、長距離・非効率な輸送ルートが多かった |
| 人手不足の影響 | 慢性的な人手不足で、1人のドライバーに過剰な業務負担がかかっていた |
一部では月間1万5000キロ、年間20万キロを超える走行例もあり、過酷さは今以上でした。
現在のトラックドライバーの走行距離
近年は社会環境の変化により、走行距離や働き方に大きな変化が見られます。
| 変化要因 | 内容 |
|---|---|
| 働き方改革の推進 | 労働基準法改正、改善基準告示の見直しで拘束時間・休息時間が厳格化された |
| IT・テクノロジー活用 | デジタコや運行管理システムの導入により、無駄な走行や待機時間が減少した |
| 高速道路・物流拠点の整備 | インフラ改善で長距離移動が効率化され、走行距離が短縮された |
| 荷主との契約改善 | 時間指定配送や共同配送の導入で、無駄な空走・待機が減った |
現在の平均的な月間走行距離は6000~9000キロ程度に抑えられ、過去に比べると大幅に改善しています。
昔と今の比較と課題
昔と現在を比較すると、以下のような違いがあります。
| 比較項目 | 昔 | 現在 |
|---|---|---|
| 月間走行距離 | 1万キロ以上が一般的 | 6000~9000キロ程度 |
| 労働時間 | 1日15~20時間、休憩不足 | 1日12~13時間、休憩・拘束時間の法規制あり |
| 待機・荷待ち時間 | 荷主依存、長時間待機が常態化 | 荷主契約改善により短縮傾向 |
| 安全管理 | 個人の技量・経験に依存 | IT管理、データ活用、安全教育の徹底 |
ただし課題も残っており、繁忙期の長距離輸送や地方便では、依然として長時間・長距離の走行が求められることがあります。
今後の展望と改善ポイント
今後、トラックドライバーの走行距離と労働環境はさらに改善が期待されています。
| 展望・改善策 | 内容 |
|---|---|
| 物流DXの推進 | 配車最適化、AI活用で効率的なルート・積載計画を実現 |
| モーダルシフト | トラックから鉄道・船舶への切替で長距離輸送を分散 |
| 人手不足対策 | 女性・高齢者ドライバー参入、外国人労働者活用で負担軽減 |
| 法規制の強化 | 2024年問題(残業時間上限規制)への対応で拘束時間短縮 |
働く人に優しい環境整備が、業界全体の課題解決につながります。
まとめ
昔と比べて、トラックドライバーの走行距離は確実に短くなり、労働環境は改善されつつあります。
一方で、依然として課題は残り、今後の改善策や業界の取り組みが重要となります。
この記事を参考に、トラックドライバーという仕事の過去・現在・未来を理解し、自分に合ったキャリア選択に役立ててください。
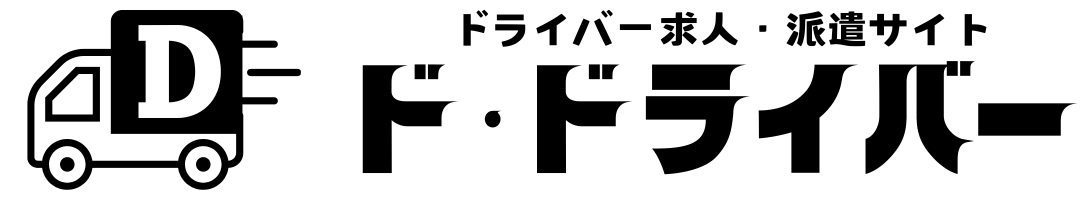





コメント