トラック運転手を目指す人や物流業界への転職を検討している人にとって、「4tトラック」「10tトラック」といった呼び名はよく目にする言葉です。しかし、これらの表記は一見わかりやすいようで、実は「車両の大きさ」や「免許の種類」とは必ずしも一致しません。勘違いしたまま資格取得を進めると、仕事に就けなかったり、違法運転につながるおそれもあります。この記事では、4t・8t・10tトラックの違いと、それぞれに必要な運転免許について詳しく解説します。
トラックの「○t」とは何を指すのか
「4tトラック」「10tトラック」という表現は、一般的に“最大積載量”を示しています。つまり、そのトラックに積める荷物の最大重量を表しており、車両の総重量やサイズを意味するものではありません。
また、同じ「4tトラック」でも、車両の年式や構造によって必要な免許が変わることがあります。
各トラックの特徴とサイズの違い
トラックは積載量だけでなく、車両の大きさや使用される現場も大きく異なります。以下に主な違いを表でまとめます。
| トラック種別 | 最大積載量 | 全長の目安 | 使用例 |
|---|---|---|---|
| 4tトラック | 約2〜4.5トン | 約7〜8メートル | 地場配送、中距離輸送、引越しなど |
| 8tトラック | 約5〜7トン | 約8〜9メートル | 中〜長距離輸送、建築資材運搬など |
| 10tトラック | 約9〜11トン | 約10〜12メートル | 長距離輸送、幹線輸送、大型貨物など |
必要な免許の種類と条件
それぞれのトラックを運転するには、車両総重量と最大積載量に応じた運転免許が必要です。以下に対応する免許区分をまとめます。
| 車両区分 | 運転に必要な免許 | 主な条件 |
|---|---|---|
| 4tトラック | 中型免許または準中型免許(限定なし) | 最大積載量4.5t未満、車両総重量7.5t未満(準中型)または11t未満(中型) |
| 8tトラック | 中型免許(限定なし)または旧普通免許(8t限定) | 最大積載量6.5t未満、車両総重量11t未満 |
| 10tトラック | 大型免許 | 最大積載量6.5t以上または車両総重量11t以上 |
なお、2007年6月の道路交通法改正以前に取得した普通免許は「中型8t限定」として扱われ、一部の中型車両まで運転が可能です。
免許選びでよくある勘違い
トラックの種類と免許の対応関係にはいくつかの注意点があります。以下のような誤解が多いため注意が必要です。
| 勘違い例 | 実際の内容 |
|---|---|
| 「4tトラックは普通免許で運転できる」 | 現行制度では準中型免許以上が必要 |
| 「大型トラックは10tトラックのみを指す」 | 積載量や総重量の条件により異なり、8t以上も大型扱いの場合がある |
| 「旧普通免許があれば何でも運転できる」 | 年式によって運転可能範囲に制限があるため要確認 |
どの免許を取得すべきかの目安
自分の希望する働き方や就職先によって、取得すべき免許が異なります。
| 目的・働き方 | おすすめ免許 |
|---|---|
| 地場配送・軽中型輸送中心 | 準中型免許または中型免許 |
| 中距離~長距離の物流業務 | 中型免許(8t以上の運転可) |
| 幹線輸送・大手物流会社勤務を目指す | 大型免許を取得するのが望ましい |
トラックドライバーとして長期的なキャリアを築くなら、大型免許の取得を視野に入れると選べる仕事の幅が広がります。
まとめ
4t・8t・10tトラックという呼び名は積載量を示す通称であり、それに応じて必要な免許も異なります。とくに近年の免許制度改正により、旧普通免許では運転できない車両も増えているため、自分の免許がどの範囲のトラックに対応しているのかを正しく理解しておくことが重要です。就職・転職前には、応募先のトラック仕様と免許条件をしっかり確認し、自分に合った免許を取得することで、安全かつ合法的に仕事をスタートさせましょう。
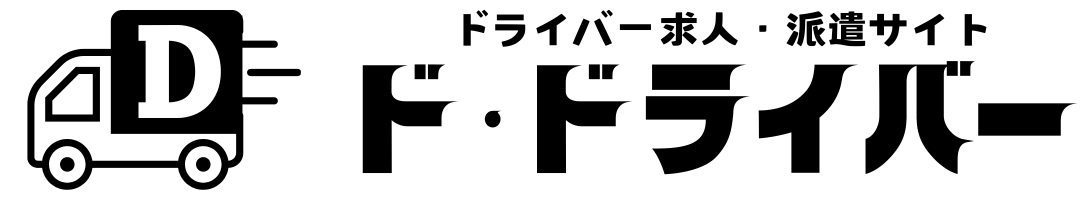





コメント